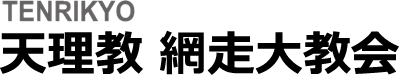世話人先生ご講話 抜粋(立教188年12月号)
ただいまは、結構に網走大教会の十一月の月次祭に参拝させていただきました。誠にありがとうございました。
また、常日頃はそれぞれの持場立場で、道の御用の上にお励みくださいまして、誠にご苦労様でございます。今日は時間を頂きましたので、思いますところをお話しさせていただきたいと思います。どうかしばらくの間お付き合いをいただきたいと思います。
三年前の十月二十六日、「諭達第四号」をご発布頂いて以来、私たちは教祖百四十年祭を目指して歩みを進めてまいりました。その教祖百四十年祭まで、いよいよあと二ヶ月余りとなりました。
教祖の年祭は、私たち人間が故人となった親やご先祖様を偲ぶためにつとめる年祭とは意味合いが異なります。
教祖は、お姿こそ私たちの目に見えませんが、今もなおご存命でお働きくだされています。ですから、年祭という同じ言葉を用いているものの、亡くなられた方、故人を偲ぶ年祭とは明らかに違いがあります。
明治二十年陰暦正月二十六日。「世界一れつの人間をたすけたい」との思召しから、二十五年先の定命を縮めてお姿をお隠しになられた子供可愛い一条の親心にお応えさせていただきたいと、この道を歩むお互いが成人の歩みを進めようとの思いで、一手一つにつとめ励むところに教祖の年祭の意義があるということは、皆さんもよく承知してくださっていることだと思います。
しかし私は、たとえ意味合いは異なっていても、人間が、自分の親やおじいさんおばあさんの年祭を我が事としてつとめるように、教祖の年祭を、私たち教祖にお導きお育ていただくお互いが、我が事としてつとめることが大切だと思っています。元々は教祖の年祭も、皆、我が事としてつとめておられたと思います。しかし、教祖が現身をお隠しになられてから年月が経つにつれ、教祖に対しての思いの持ち方、年祭についての考え方も少しずつ変わってきているような気がいたします。
今申した、教祖の年祭の意義は知っていながら、大切だと思いながら、どこか我が事から遠くなってきている気がするのです。
真柱様は、立教百八十五年、年頭のご挨拶の中で「私たちが先人の苦労を忘れ、結果として、教祖が遠くなってしまったというところがあるのではないかと思うのであります」とお話をくださいました。
私自身の常日頃の通り方の中でも、父や母の姿勢と比べると、教祖が遠くなっているのではないかなと反省をするところがあるのですが、教祖の年祭ということに関しても、人間の年祭とは違うんだということを強調するがあまり、私たちの親である教祖の年祭なんだ、自分の親の年祭なんだという親しみが薄れてきている、そんな感じがいたします。
教祖は、親神様が人間をお創りくださった時、母親の役割を務められた魂をお持ちの方であります。そして、月日のやしろと定まられてからは、人間の元の親、実の親であらせられる親神様が入り込まれたお方であります。
親神様、教祖にとって、子供である私たちが、陽気ぐらしへの道を誤らずにたどれるように、自ら五十年に渡って道を歩んでくださったひながたの親が教祖であります。つまり、教祖は私たちみんなの親であらせられる。自分の親なんだ。こうしたことを何よりも大事にさせていただきたいと思います。
人間の年祭は、故人が出直された日を基準につとめるのですが、教祖の年祭は、教祖がお姿をお隠しになられた日が元一日であります。教祖百四十年祭が近づいた今、今一度、明治二十年陰暦正月二十六日に思いをいたしてみたいと思います。
明治十九年陰暦十二月八日の夕方、教祖は風呂場からお出ましの際にふとよろめかれました。そして陰暦十二月十一日、急に教祖のご身上が迫ってくるという状況が現れてきたのです。以後、明治二十年正月二十六日に至るまでの一ひとつき月余り、教祖のご様子は一進一退と申しますか、どんな日もあったように思います。
そうした中、当時のお屋敷の人々は、つとめの実行を急き込まれる教祖のお心をひしひしと感じながらも、官憲の干渉との間に挟まれて、なかなか思召通りに通り切れない日々を過ごしておられました。その様子は、『稿本天理教教祖伝「第十章
扉開いて」』に記されている通りであります。
陰暦十二月二十日には、初代真柱様が直接教祖と問答をなされ、その中で「親神様の仰せと国の掟と、両方の道の立つようにさしづをお願いします」と自らの苦しい胸の内を打ち明けられました。
すると教祖は、「親神の話をしっかり聞いて心を定めることが一番大切なのだ。今という今、抜き差しならぬ時にあたっては、心を定めることが一番肝心である。心さえ定まれば、道はいずれ開けてくる」という意味のお話をしてくださいました。
さらに、だんだんと問答が積み重ねられていく中、初代真柱様はついに、「この屋敷に道具雛型の魂生まれてあるとの仰せ。この屋敷をさして、この世界始まりのぢば故天下り、無い人間無い世界を拵え下されたとの仰せ。かみも我々も同様の魂との仰せ。この三ヶ条の訪ねがあればなんと答えれば良いのですか。人間は法律に逆らうことはかないません。」と当時の人たちにとって一番苦しいところを口に出し、どうすれば良いのかと縋り付かれたのです。
そして、この時くださったお言葉が、「さあさあ月日がありてこの世界あり、世界ありてそれぞれあり、それぞれありて身の内あり、身の内ありて律あり、律ありても心定めが第一やで」というものでありました。
これは何よりもまず、親神様がおられてこの世界が生まれた。そして、世界が生まれてから国々ができ、そこに人々が親神様から身体を借りて生活をしている。その人々が住み暮らしやすいように申し合わせて作ったものが法律である。そこにどんな法律があったとしても、それを活用するかどうかは人々の心の問題である、という意味だと思います。
つまり、親神様が人間世界をお創りくださったことが全ての元である。そしてどんな状況にあっても、一番大切なのは人々の心なんだ。この一連の順序を胸に治めて、親神様に通じる心をしっかりと定めることが何より大切だ、と教えてくださったと悟るのであります。
この問答のあった日以降、教祖は小康状態を保ちながら毎日をお過ごしくださり、陰暦正月元旦には、随分ご気分もよろしくなられたのであります。
ところが正月二十五日夜、教祖のご身上はよろしくなく、人々は飯降伊蔵先生を通して神意を伺われました。その時のお話の中で、「さあさあ扉を開いて地を均らそうか、扉を閉まりて地を均らそうか均らそうか」とのお言葉がありました。一同は、扉を開く方が陽気でよかろうとの思いがあったのか、まさかそのことが教祖が現身をお隠しになることに繋がるとは思いもせず、「扉を開いてろくぢにならしくだされたい」と返事をなされたのであります。
教祖が人々に急き込まれていたのは、何が何でもおつとめをつとめるということでありました。しかしおつとめをつとめることは、教祖がお望みくださっていることだ、大切なことなんだとわかっていながら、人々は素直に実行することができなかったのです。
そこには、「おつとめを堂々とつとめれば必ず警察がやってくる。そうなれば自分たちをたすけてくださった何よりの恩人、生き神様である教祖が連れて行かれる。しかもその教祖は、ご高齢でご身上である。だからそれだけはどうしても避けたいし、避けなければならない。」との考えがあったのだと想像いたします。
教祖の身を慮るが故の人々の思案と、おつとめを実行すること、教えを教え通りに実行することを何よりも求められる教祖の思召とは、同じような方向を向きながらも大きな開きがあったと言えるでしょう。その開きが、教祖と初代真柱様との問答などを通して、少しずつ縮まってきたのだと思います。
こうして、いよいよ正月二十六日を迎えることになりました。二十六日はそれまでも、毎月おつとめをつとめてきた日ではありましたが、人々はこうした状況の中でもつとめるべきなのかどうか思案に暮れ、神様の思召を伺われました。
そこで頂いたお言葉は、「もう悠長なことを言っている場合ではない。お前たちは法律が怖いのか、神の話が尊いのか、どちらに重きを置いて信心しているのだ。親神の思いは、前々から十分に説いてきた。今の刻限は、もう尋ねている時ではない。これだけ言ったら分かるだろう」という意味のものでした。
人々はこれでいよいよ心が定まり、初代真柱様の「おつとめの時、もし警察よりいかなる干渉あっても、命捨ててもという心の者のみ、おつとめをせよ」との言葉のもと、意を決しておつとめにかかられました。
この時のおつとめは、形の上では必ずしも教えられた通りの姿ではありませんでしたが、人々の心の真実をお受け取りくだされたのでしょう。日中に堂々とつとめたにも関わらず、警察がやってくることはなかったのであります。
しかし、人々が思いもしなかったことが起こりました。それは、ちょうど十二下りの最後のお歌が終わる頃、教祖が現身をお隠しになられたということでした。二代真柱様の著書である『ひとことはなし
その二』という本の中に、当日の様子が記されていますので、それを参考に少しお話をしてみたいと思います。
その頃教祖は、明治十六年に建てられたご休息所という建物で毎日を過ごされていました。
始終お世話をなされていたのは、教祖の長女おまさ様と孫の梶本ひさ様(教祖の三女おはる様の娘様)でした。ご気分が悪くなられてからは、初代真柱様もおそばにおられたようです。その頃十歳ぐらいだったたまへ様(長男秀司様の娘様で、後に初代真柱様のご夫人となられた方)であります。この方は教祖の様子が気になって、中を見ようと障子を開けては叱られたんだと語り遺しておられます。
正月二十六日のおつとめは、もちろんぢばのところでつとめられました。今、記念建物の一つとして残されているつとめ場所は、かんろだいがここにあったという場所が建物の中にありますが、これは後に増築をされて取り込まれたのでありまして、明治二十年当時かんろだいは、つとめ場所の外にあったのであります。かぐらづとめは、かんろだいを囲んで。十二下りは南から北向きに(今、本部の神殿でつとめておられるのと同じ向き)つとめたということです。
おひさ様が言われるには、陽気なおつとめの声を聞いて、教祖は心地よさそうにお休みになっておられたので、おそばにいたおまさ様は参拝に出ていかれました。
そして、「だいくのにんもそろひきた」と十二下り目が終わる頃、教祖がちょっと変なそぶりをなされたので、おひさ様が「お水ですか?」と尋ねたが返事はなく、それでも水を差し上げると三口召し上がれました。「おばあ様」と重ねて呼んでも返事はありません。そこで「誰か居ませんか。
早く真之亮さんを呼んできてくだされ」と叫ばれたのであります。そうこうしているうちに、おまさ様や初代真柱様が戻って来られたのであります。
一方、おつとめに出られたたまへ様は、おつとめが終わると、「教祖はもう良くなってくださったかな。ご飯も召し上がってくださったかな。」とご休息所へ戻られました。「仰せ通りにおつとめをつとめたのだから、教祖の身上は良くなっているに違いない。」これがおつとめをつとめた人たちの、正直な気持ちだったと想像をいたします。
しかし結果は違いました。たまへ様がお部屋を覗くと初代真柱様に、「早よ来い」と呼ばれ、おひさ様から「おばあ様がこんなになられた」、「冷たいんやな。おばあ様はもの言わはらへんねがな」と言われ、教祖が現身を隠されたということを知った、ということであります。
たまへ様は「子供心に、今にも天地が闇になるかと思いながら、まだ明るいまだ明るいと思った」と語られていたが教祖が現身をお隠しになることに繋がるとは思いもせず、「扉を開いてろくぢにならしくだされたい」と返事をなされたのであります。
教祖が人々に急き込まれていたのは、何が何でもおつとめをつとめるということでありました。しかしおつとめをつとめることは、教祖がお望みくださっていることだ、大切なことなんだとわかっていながら、人々は素直に実行することができなかったのです。
そこには、「おつとめを堂々とつとめれば必ず警察がやってくる。そうなれば自分たちをたすけてくださった何よりの恩人、生き神様である教祖が連れて行かれる。しかもその教祖は、ご高齢でご身上である。だからそれだけはどうしても避けたいし、避けなければならない。」との考えがあったのだと想像いたします。
教祖の身を慮るが故の人々の思案と、おつとめを実行すること、教えを教え通りに実行することを何よりも求められる教祖の思召とは、同じような方向を向きながらも大きな開きがあったと言えるでしょう。その開きが、教祖と初代真柱様との問答などを通して、少しずつ縮まってきたのだと思います。
こうして、いよいよ正月二十六日を迎えることになりました。二十六日はそれまでも、毎月おつとめをつとめてきた日ではありましたが、人々はこうした状況の中でもつとめるべきなのかどうか思案に暮れ、神様の思召を伺われました。
そこで頂いたお言葉は、「もう悠長なことを言っている場合ではない。お前たちは法律が怖いのか、神の話が尊いのか、どちらに重きを置いて信心しているのだ。親神の思いは、前々から十分に説いてきた。今の刻限は、もう尋ねている時ではない。これだけ言ったら分かるだろう」という意味のものでした。
人々はこれでいよいよ心が定まり、初代真柱様の「おつとめの時、もし警察よりいかなる干渉あっても、命捨ててもという心の者のみ、おつとめをせよ」との言葉のもと、意を決しておつとめにかかられました。
この時のおつとめは、形の上では必ずしも教えられた通りの姿ではありませんでしたが、人々の心の真実をお受け取りくだされたのでしょう。日中に堂々とつとめたにも関わらず、警察がやってくることはなかったのであります。
しかし、人々が思いもしなかったことが起こりました。それは、ちょうど十二下りの最後のお歌が終わる頃、教祖が現身をお隠しになられたということでした。二代真柱様の著書である『ひとことはなし
その二』という本の中に、当日の様子が記されていますので、それを参考に少しお話をしてみたいと思います。
その頃教祖は、明治十六年に建てられたご休息所という建物で毎日を過ごされていました。
始終お世話をなされていたのは、教祖の長女おまさ様と孫の梶本ひさ様(教祖の三女おはる様の娘様)でした。ご気分が悪くなられてからは、初代真柱様もおそばにおられたようです。その頃十歳ぐらいだったたまへ様(長男秀司様の娘様で、後に初代真柱様のご夫人となられた方)であります。この方は教祖の様子が気になって、中を見ようと障子を開けては叱られたんだと語り遺しておられます。
正月二十六日のおつとめは、もちろんぢばのところでつとめられました。今、記念建物の一つとして残されているつとめ場所は、かんろだいがここにあったという場所が建物の中にありますが、これは後に増築をされて取り込まれたのでありまして、明治二十年当時かんろだいは、つとめ場所の外にあったのであります。かぐらづとめは、かんろだいを囲んで。十二下りは南から北向きに(今、本部の神殿でつとめておられるのと同じ向き)つとめたということです。
おひさ様が言われるには、陽気なおつとめの声を聞いて、教祖は心地よさそうにお休みになっておられたので、おそばにいたおまさ様は参拝に出ていかれました。
そして、「だいくのにんもそろひきた」と十二下り目が終わる頃、教祖がちょっと変なそぶりをなされたので、おひさ様が「お水ですか?」と尋ねたが返事はなく、それでも水を差し上げると三口召し上がれました。「おばあ様」と重ねて呼んでも返事はありません。そこで「誰か居ませんか。
早く真之亮さんを呼んできてくだされ」と叫ばれたのであります。そうこうしているうちに、おまさ様や初代真柱様が戻って来られたのであります。
一方、おつとめに出られたたまへ様は、おつとめが終わると、「教祖はもう良くなってくださったかな。ご飯も召し上がってくださったかな。」とご休息所へ戻られました。「仰せ通りにおつとめをつとめたのだから、教祖の身上は良くなっているに違いない。」これがおつとめをつとめた人たちの、正直な気持ちだったと想像をいたします。
しかし結果は違いました。たまへ様がお部屋を覗くと初代真柱様に、「早よ来い」と呼ばれ、おひさ様から「おばあ様がこんなになられた」、「冷たいんやな。おばあ様はもの言わはらへんねがな」と言われ、教祖が現身を隠されたということを知った、ということであります。
たまへ様は「子供心に、今にも天地が闇になるかと思いながら、まだ明るいまだ明るいと思った」と語られていたで言ってきたんや」と言われたのです。
こうしたお話には、当時の人たちの信仰の様子が大変よく現れていると思います。
真実の親として、また地上の月日として崇めお慕い申していた教祖が、現身をお隠しになったことを聞いた時、もうこれまでのようにお声を聞くことができないと知った時の衝撃は、教祖のお姿を拝したことのない私たちには想像もできない大きなものだったと思います。
今もありましたが、人々は「教祖は必ず百十五歳までおいでくださる」「こうしておつとめをさせていただいたんだから、必ず元気になってくださる」と信じていたのでしょう。稿本教祖伝には、「全く、立って居る大地が砕け、日月の光が消えて、この世が真っ暗になったように感じた」と記されているのです。
そうした中、飯降伊蔵先生を通して伺われたおさしづで、「子供可愛いばかりに、その心の成人を促そうとして、まだ二十五年ある命を縮めて身を隠したのだ。今から世界を駆け巡ってたすけをする。今までとこれから先とどう違ってくるかしっかりと見ていよ。昨日、扉を開いて地を均らそうか、それとも閉めて地を均らそうかと尋ねた時に、開いてくださいと言ったではないか。親神は心通りに守護したのである。さあ、これまでは子供にやりたいもの(これはおさづけのことです)もあったが、思うように授けることができなかった。これから先だんだんに渡していこう」という意味のお言葉を頂戴なさったのです。
このお言葉を通して、教祖は子供可愛い故に姿を隠されたこと、たとえ姿を隠されても世界を駆け巡って一れつをたすけるためにお働きくださること、つまり、これから先は扉を開いて世界たすけにご存命のままお働きくださることをお教えいただいたのであります。
このことが人々の心に治まるまでには、時間を要したかもしれません。しかし「扉を開いて働いてくださる」「姿は見えないけれど働いてくださる」ということを頼りに、ご存命の教祖をお慕いして通るという信仰姿勢が、この時から始まっていったのです。
今を生きる私たちも、「教祖は人々の心の成人を促そうと、その現身をお隠しになられ、世界だすけにお踏み出しくだされたんだ」「教祖はお姿こそ拝せないものの、今尚ご存命でお働きくださっているんだ」と聞かせていただき、そのことを信じてこの道を通っているのです。
しかし、教祖はご存命だということを信じることは、年月が経つとともに難しくなってきているのではないかと思うことがあります。また、それを信じる力が年々弱くなってきているということも否定できないように思います。
先ほど来お話した事柄は、教祖五十年祭の頃に二代真柱様が、たまへ様や高井先生に聞かれたのであります。その頃はまだ、明治二十年の様子を直接知っている人が、少ないながらも残っておられました。
それから九十年近くが経っているわけですから、もちろん今は、明治二十年を知っている人は誰もいません。教祖五十年祭の頃の様子をはっきり覚えているという人も、ほとんどおられないでしょう。それでも教祖は、今なおご存命でお働きくださっているのです。そのお働きは、お姿をお隠しになられて以来、少しも変わっていないのです。そのことをひたすら信じて通ることが、私たちの信仰の源であると申したいのです。
さて皆さんは、初めておぢばに帰られる方を案内する時、本部の教祖殿で、教祖のことをどのように説明されるでしょうか。もちろん、月日のやしろとして親神様の教えを私たちに教えてくださった方である、ということはお話されるでしょう。そして、今もご存命でお働きくだされているんだ、ということも必ず説明をなさると思います。
今もここにお住まいくださって、三度のお食事からお風呂、ご寝室に至るまで、お姿があるのと同様になさっているんですよ、というようなことを説明されるのではないでしょうか。その時、教祖のお社の前に赤衣が見えれば、そのことにについてお話をされる方もあるかと思います。
教祖がご存命でお働きくださっているということは、この道の信仰の上で欠かすことができないと皆承知をしているのです。だから、必ず教祖はご存命だということを人に説明するように心がけているのでしょう。
では、教祖がご存命でお働きくださっているということをどんな時に感じますか、と問われたら、どう答えるでしょうか。私は自分が教祖殿で参拝をしている時に、それを実感することがあるのです。教祖殿には毎日たくさんの人が参拝に来られます。参拝に行った時、合殿にも御用場にも、自分以外に誰も人がいないということは、日中ならあまりないような気がいたします。参拝に来られる人の中にはお礼を申し上げる人、相談をなさる人、また縋りつくようにたすけを求める人など、いろんな方がおられるでしょう。
私も、その時その時で中身は異なりますが、いろんなことを申し上げているのであります。教祖なら何でも聞いてくださるに違いないと思い、人には言えないことでも申し上げることもあります。
そうして参拝をしている時、私は周りで他に参拝している人がいても、あたかも自分が教祖と一対一で話をしているような気になります。周りにどれだけの人がいようが気にはなりません。
きっと教祖も同じ時に何十人、何百人の人が参拝していたとしても、それぞれの話を、皆一対一で聞いてくださっていることでありましょう。
私はこれも、現身をお隠しになられて世界たすけに踏み出された一つの証ではないかと考えるのであります。
もし今、教祖のお姿をこの目で拝することができるなら、やっぱり直接話を聞いていただきたいと思います。並んで順番待ちだってすると思います。でもお姿を隠された今は、その必要はありません。いつでも、誰でも、どこにいても、その気になれば教祖とお話することができるのであります。これも、ご存命でお働きくださるからこそのことだと思います。
教祖が今尚、ご存命でお働きくださる。そのことを実感をすることは、私たちの信仰の大きな力となります。しかし何の努力もせずに、「実感したい実感したい」と呟いているだけでは、なかなかその機会はやってこないと思います。
教祖のお働きを自分の身に感じるためには、やはり親神様の教えを実践する努力、身に行う努力が欠かせません。
中でも、おつとめをつとめ、おさづけの理を取り次ぎ、にをいがけおたすけに励む中でこそ、教祖のご存在を感じさせていただける機会を頂戴できるのだと思います。
ここで私が初めて、にをいがけおたすけに際して、教祖のお働き、またぢばのありがたさを実感した話を少しさせていただきたいと思います。
私は生まれた時からお道の環境の中で育ち、高校まではずっとおぢばの学校に通っていましたから、言葉の上では少しは教えを知っているつもりでありました。そうした中、二十四歳の時に布教の家に入れてもらいました。三十年以上も前の話です。
布教の家での一年間は、人をお連れしてでなければおぢばへ帰ることができません。いくら通い先ができても、「是非おぢばへ帰りましょう」という一言が言えなければ次に進めないのです。
この時になって初めて、自分が親神様、教祖、ぢば、そうしたところに、どこまで自信を持って人に話ができるのかということに向き合うことになりました。
ぢばには、私たち人間の元の親、実の親であらせられる親神様がお静まりくださり、子供である私たちが、親里へ帰ってくるのを楽しみにお待ちくだされています。
私たちはその親の元へ、すなわち親里へ、親を慕って、親を頼りに、真実の心を持って帰らせていただくのです。それがおぢば帰りです。
こうして帰ってくる子供と、帰りをお待ちくださる親の双方の心が通い合う時に、親神様は不思議なめずらしいたすけをお見せくださるのであります。私も、そういう話は何度も耳にしたことがありました。でも実際に、そのありがたさを肌で感じたことは、それまでは一度もなかったのであります。
ちょうど、教祖百十年祭の三年千日の一年目でした。布教の家にいたおかげで、年祭を意識して毎日を過ごすことができていたようには思います。しかし、だからと言って簡単ににをいがかかり、おぢばへ帰ってくれる方をお与えいただけるわけではありません。子供おぢばがえりなど、団参というような形で帰ることはできたのですが、自分が直接にをいをかけた人を誘ってのおぢば帰りはなかなかできませんでした。
それでも、布教の家での生活が終わる三月になって、ようやく通い先の人がおぢばに帰ってくれることになりました。その方は、ひどいヘルペスを患っておられまして、家にいて話をしていても、十分、十五分と話をしていると、一度は必ず痛さで顔を歪めるという感じでありました。毎回おさづけの理を取り継がせていただくのですが、「おかげで痛みがマシになった」と言ってくださる日もあれば、「拝んでもらってもあんまり変わらない」と言われることもありました。
この時のおぢば帰りは一泊二日で、その帰りの電車の中でのことです。あれこれと話をしながら、ふとあることに気が付きました。「そういえば、この人この二日間一言も痛いと言わんかったなあ」と。そのことを本人に伝えると、とても不思議そうな顔をして、「そういえばそうやなあ。全然痛みがなかったわ」と自覚をされたのです。
「ほんまに鮮やかやなあ」と思わずにはいられませんでした。おぢばに帰ってくださったことに、親神様、教祖の元に帰らせていただいたことに、鮮やかな印をお見せくだされたのであります。
「親里ぢばはたすかるところ、たすけてくださるところというのは本当やな。親神様、教祖は、子供が帰ってくるのを楽しみにお待ちくだされているというのはほんまなんやな」と心からそう思いました。
それ以降も、こうしたありがたさを感じることに出会ってはいるのですが、最初に実感できたのはこの出来事だったように思います。
やはり、頭で理屈を考えるだけでなく、にをいがけ・おたすけに一生懸命になっている時にこそ感じさせてもらいやすいように思います。
以降、百二十年祭、百三十年祭と年祭の経験いたしました。どの年祭も与えられた持場立場で、意識をして務めさせてもらったつもりであります。しかし、振り返れば反省ばかりです。こうして通らせてもらおうという心が続かなかったり。教祖にお喜びいただきたい、という心がいつの間にか薄くなってしまったり、本当に届かぬことばかりであります。今回でもまだまだできてない、そう思っています。
私は教祖百年祭の時の母親の姿が忘れられません。当時は一月二十六日から二月十八日まで、年祭の期間として毎日おつとめがつとめられていました。初日と最終日のどちらの日だったかは覚えていないのですが、おつとめの時に母がポロポロと涙を流していました。
それが忘れられません。なぜ涙を流していたのか聞いていないので分からないのですが、きっと教祖をお慕いするからこその涙、一生懸命通ってその日を迎えたからこその涙だったと思っています。母も、もちろん教祖をその目で見たことはありません。でもそんな涙を流せるのであります。お姿を知らないから、お声を知らないから信じきれない、慕う心が弱くなる、と言っているようでは、後々の人が安心して通れるようにと、五十年のひながたを残してくださった教祖に、何か申し訳ない気がするのであります。
今私たちは、「おやさま」を漢字で表す時には「教きょうそ祖」という字を書いています。「教きょう祖そ」という字を「おやさま」と読むことは、今から八十年近く前、現在の「天理教教典」が作られた時からだと聞いています。
それまでは「おやさま」中山みき様のことを「教きょうそ祖様」あるいは「おやさま」とお呼びすることがあったのですが、「教きょうそ祖」という字と「おやさま」という呼び方をつなげたのはこの時だったようです。
ある辞書を開いてみますと、「教きょうそ祖」という言葉の意味は「ある宗教、宗派の創始者。開祖」と記されていました。
教おやさま祖は、親神様の御教えを私たちに伝え、この道をおつけくださった方でありますから、「教きょうそ祖」であります。また「おやさま」は私たちの親でやらせられるお方ですから、「おやさま」と呼びするのは自然なことであります。
「教きょうそ祖」という意味と「親」という意味を一つの言葉で表現する「教おやさま祖」と「おやさま」。この二つを結びつけられたのは、この教えを始めてくださった「おやさま」は私たちの親なんだという親しみをもっと持ってもらいたい、という思いからだったのではないかと思っているのであります。
これも二代真柱様の著書である『続ひとことはなし』という本の中に、教祖がお姿を隠される前は教祖のことを「おやさま」あるいは「かみさま」と申し上げていた、と古い先生が語られていたと記されています。
さらには教祖殿にお参りすることを、「おやさんへ参る」と言ったりもしていた、とも記されてありました。「おやさん」というのは、「おやさま」がなまった言葉だと思います。「おやさま」「おやさん」という呼び方にはどこか私は温かさを感じます。私にとってもこの「おやさん」というのは、子供の頃から耳慣れた懐かしい言葉でもありますし、意識はしていませんが、きっと今でも知らないうちに自分で口にしていることがあると思います。
最初の方にも申しましたが、私は教祖は私たちの親だと思っています。親だからこそ、単に優しいだけでなく、時には厳しく、でも温かく、深く、広く、親心いっぱいで私たちを見守ってくださっていると信じています。
おふでさきに
にんげんのわが子をもうもをなぢ事
こわきあふなきみちをあんぢる(七―九)
というおうたがあります。
私は、親神様・教祖と私たちの関係を、人間の親子の関係と同じように考えると分かりやすいし、神様の親心も想像しやすいと思っています。
私たちが自分の子供のことを大切に思い、いろいろと心配するのと同じように、親神様、そして月日のやしろたる教祖も、我が子である私たちのことを可愛く思い、神様の目から見て、危ない道に彷徨うことのないように、あれこれとお心を配ってくださっているのでありましょう。
昔と今では、人間の子供の育て方が随分変わってきていると思いますが、子供を育てるにあたって、一度も注意をしたことがないという人はいないように思います。注意の仕方は人によって違うでしょう。
厳しく言う人もあるでしょうし、優しく言う人もあると思います。でも、いずれの場合も子供の側から見れば、注意をされるということは、自分のしたことを、ある意味否定されるのですから面白いことではありません。嫌な思いをするのだと思います。
でも親は、このままでは子供の為にならないと思うから意見をするのです。憎いから注意をするのではありません。嫌いだから叱るのでもありません。それは、可愛いからこそ、子供のためを思うからこその行いなのであります。
親神様、教祖も同じだと思います。私たち一人一人の、いんねんも含めたこれまでの通り方を見て、また、将来まで見据えた上で、その時その時にふさわしいことを教えてくださるのです。
褒めてくださる時は、嬉しい姿を見せてくださるのでしょう。このままではいけないという時には、身上や事情に表して注意を促してくださるのだと思います。嬉しいことも楽しいことも、辛いことも悲しいことも、めんどくさいことも、全て子供可愛い一条の親心からお見せくださっているのであります。
私たち人間の子育ては、こうした方がいいのか、ああした方がいいのか悩むことがあります。時には判断を誤ることがあるかもしれません。しかし、親神様・教祖が私たちを育てるにあたってお見せくださることは、決して間違いがないと信じています。
私たちが気がつかないようなところまで見通して教えてくださっているのですから、こちらがうまく受け止めることができずに不足をしてしまうこともあるでしょう。それでも、間違いがないんだと信じる姿勢が大切なのだと思います。
繰り返しになりますが、教祖は私たちの親であらせられます。だから、親を慕えばいいのであります。お姿が見えないから、お声が聞こえないからといって、距離を感じすぎる必要はありません。敬して遠ざけるのではなく、自分から近づき、甘え、凭れればいいのだと思います。そうすれば必ずお応えくださる、そう信じます。
子供の方から、近づいていこうというその態度、姿勢をきっとお喜びくださるのだと思います。こちらから近づこうとすればするほど、「教祖はご存命なんだ」と感じることに出会わせてくださるでありましょう。反対に、近づくことを遠慮すれば遠慮するほど、ご存命ということが分からなくなってしまう気がいたします。
さあ、教祖百四十年祭まで、残すところ本当にあとわずかの時間となりました。しかし、明日が百四十年のその日だというわけではありません。まだ二ヶ月余りあるのであります。お互いが、定めた目標に向かってしっかりと務め切らせていただきたいと思います。
精一杯、教祖に近づく努力をして、お慕いする努力をして、それこそ自分の親の胸に飛び込むような気持ちでその日を迎えることができるように、最後の最後までしっかりと通らせていただきましょう。そのことをお願いして、今日のご挨拶と変えさせていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。