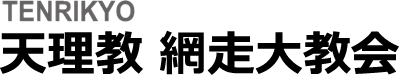大教会長様講話(立教188年2月号)
天理教の中心的立場になられる真柱様は、今から三年前の十月二十六日に我々信仰するものに対して、来年迎える教祖百四十年祭までの三年間、このような心で日々を通って欲しいということで、「諭達第四号」を発布して下さいました。
この「諭達第四号」では冒頭に、真柱様の思う所を述べて、天理教を信仰する者の心を一つにしたいと述べられています。そして教祖百四十年祭のその日までの心掛けを詳細に示して下さいました。
内容としましてはまず、旬刻限の到来ということで今から十億年少し前より、天理教が始まるのは百八十八年前の十月二十六日と決まっており、世界中の全ての人間の母親の魂をもった教祖の身体に親神様がお入り下さり、親神様は姿形も見えないし声も聞こえないので、教祖の身体や口を通して今ままでの学問では聞いたことのない様々な話や、信仰の根本、大切なおつとめについて教えて下さいました。
そして教祖は、ただこうしなさいと人に言うだけではなく、自ら親神様から教えて下さったこの教えを実行されました。その年数はおよそ五十年になります。この教祖が通られた五十年の道中を我々信仰するものはひながたの道と呼んでおります。
更に教祖は天理教が始まり五十年で出直し、いわゆる亡くなるということですが、そうではなく今から百三十八年前の一月二十六日に体、即ち姿だけは隠されたが今も存命でこの世に生きていて、おぢばに留まり、世界中の人間をたすけて下さり、我々を導いて下さっていると「諭達」の一頁〜二頁に渡って記して下さっております。
そして真柱様は教祖百四十年祭を勤める意義について、我々ようぼく一人ひとりが教祖の手足となって、年祭までの三年間と仕切って、今までできなかったことや、やろうと思っていたが後回しにしていたことを実践し成人すること、信仰者として成長することが年祭の意義なんだとお示し下さいました。
それから先程話した、教祖の通られた五十年のひながたの道を我々も通らせてもらわねばならない。特にこの三年間はひながたの道より通る道はない。と親神様のお言葉を上げられお示し下さいました。
続いて真柱様は「諭達」の三頁目で、教祖はひながたの道をまず貧のどん底に落ちることから始められたけれども、どんな困難な中でも常に心明るく通られましたと仰せ下さり、たくさんある五十年のひながたの例から三つ挙げて下さいました。
一つ目は「水を飲めば水の味がする」ということです。これは天理教が始まった前後は、大きな大飢饉が度々起こる時代で、飢饉が起こる度、道端にはそこら中に亡骸が転がっているような状況でした。
その中、親神様より「物を施し執着をされば、心に明るさが生まれ、心に明るさが生まれると、おのずから陽気ぐらしへの道が開ける」とのお言葉を実行され、教祖はありとあらゆるものを困っている方々に施され、終いには僅かに残った明日食べる米すら全て貧困に苦しむ人に分け与えてしまいました。
この時娘のこかん様が「お母さん、もうお米はありません」というと、教祖は「世界には枕元に食べ物を山ほど積んでも、食べるに食べられず、水も喉を通らないといって苦しんでいる人もいる。そのことを思えば私らは結構だよ。水を飲めば水の味がする。親神様が結構に与えて下さっている」というようなお話をして下さいました。
これは我々が毎日健康でいられるのが当たり前と思っているが、全ては親神様が日々生きる為に必要な働きをして下さっているから、健康でいられるので、体を含め現在のこの状況に感謝させてもらおうと教えて下さっています。
二つ目は「ふしから芽が出る」ということです。これは木の節に例えての話しですが、木には必ず節があります。節から新しい芽が出て枝が太くなり更にその枝からまた節ができて新しい芽が出て、葉が沢山ついた大きな木へと成長していきます。
人生も同様で災難や病難、人間関係の難や仕事の難など生きていれば様々な節があります。辛いことばかりかもしれませんがこの人生の節は、我々が成長しいつか大きな木になるための節で、親神様がそれぞれに乗り越えられる節を用意して下さり、励まして下さっていると教えて下さっています。
三つ目は「人救けたら我が身救かる」ということです。我々は辛くてどうにもならない苦しいことが起こると、ついつい周りの人のせいにしたり、物事のせいにしたりします。
しかし冷静に考えると案外周りのせいではなく、自分が原因で起きてしまっていることに気づかされることがあります。このような時こそ教祖は「人救けたら我が身救かる」という教えを実行してくれと教えて下さいました。しかしこれはなかなか簡単なことではありません。自分自身がもがき苦しんでいる状態で、人のことを考えなさいというのは、大変酷なことをしなさいということになります。
しかし今のままではどこまでいっても苦しみや悩みからは逃れることができないので、まずは思い切って人の幸せを願ってみる、人がたすかるように祈ってみる。この行動こそ気づけば心が澄んでいき運命が変わり、明るい人生のきっかけになると教えて下さいました。
他にも教祖のひながたには沢山、幸せになる心の使い方がありますが、この五十年のひながたこそ陽気に暮らすための唯一の道だと「諭達」でお示し下さっております。
そして五頁目で真柱様は現在の状況について、世の中には周りへの思いやりを欠くような自分中心の主張や後先を考えずに、今この瞬間だけを充実させればよいという刹那的な行動があふれ、そのことが原因で自分の力を過信しその結果、心の闇の中でさまよっている人々がいるとご指摘下され、親神様はこうした人間の心得違いを知らせる為に、病気や悩みまた自然災害や世界的に流行している疫病を通して、早く自己主張や刹那的行動を改めてくれと、これは世界中の人間である親神様の子供達が可愛くて、可愛くて仕方ないという親心の現れであるとお示し下さいました。
そして親神様は今こそ皆が立て合って、共にたすけ合う陽気ぐらしを求めらているとのことであります。
最後に我々信仰するようぼくに対して具体的にこうして欲しいと六つの例をあげて下さいました。
一つ目は進んで教会に参拝をすることです。近くに教会があれば一回でも多く参拝させてもらい、行く先々で教会があればちょっと立ち寄って参拝させて頂きましょう。
二つ目は日頃からひのきしんに励むことです。例えば毎日三度のご飯を作るのはもううんざりという方もおられるかもしれません。しかしご飯を作る前に手を合わせて、親神様これからご飯を作らせて頂きますと心で唱えれば、三度三度作るご飯が、ひのきしんに変わります。職場での掃除や家事などどんなことでも神様に感謝の心を持ちながら行動することはすべてひのきしんとなります。
三つ目は家庭や職場など身近なところからのにをいがけです。これは普段使わせて頂いている耳に感謝して人の話を聞かせて頂く、相手が明るくなるような神様が好む言葉を、お借りしている口から出す事でにをいがけになります。
四つ目は病気や様々なことで悩み苦しんでいる方は大勢いるはずです。その方に対して自分のことだと思って寄り添い、その人がたすかるようにお願いづとめすることです。お願いづとめは一回するのに五分から十分もあれば終わります。一日のうちたったの五分、十分です。我々信仰するものは人の為にせめて五分や十分位は祈る時間を御供させて頂きましょう。
五つ目は病で苦しむ人へおさづけを取り次ぐことです。教祖は世の中の人達を救けたくて救けたくて仕方がありません。この教祖の思いを心に教祖の手足となっておさづけを頂いたようぼくになる我々が、とにかくこの仕上げの一年、一人でも多くの方へおさづけを取り次がせて頂きましょう。
六つ目は親から子、子から孫へこの素晴らしい教えを伝えることです。子供や孫へ伝えることは沢山あります。例えばまずは朝、目が覚めたことが有難いねと伝えたり、ご飯を味わえることが有難い、一緒にお風呂に入った時には火と水の働きがあるからお湯になり有難いまた、トイレに行った後神様の働きで出たことが有難いと毎日当たり前のようで、当たり前ではない神様の働きによって生かされていることを伝えさせて頂きましょう。
この「諭達第四号」の6つの具体例を目で見える形となる実動報告書を親神様・教祖へ上げさせて頂き、網走大教会に繋がるもの一同が一生懸命実動することにより理づくりや種まきとなり、年祭活動三年目の仕上げの年に大きく拍車がかかり、本年大教会の心定めにあたる初席者五十一名、ようぼく二十三名、修養科修了者十八名、教人六名の達成へとご守護が頂けるのであります。この心定めはすべておぢばへ、定めた方々をお連れさせて頂いて初めて達成するわけであります。
おぢばへ帰らなければ、別席の話しも聞けませんし、おさづけを頂戴してようぼくになることもできません。修養科や教人講習会もおぢばでしか行われておりません。まずは悩み苦しむ方や何の為に生きているのかすらわからない人達へ真にたすかる場所があることを伝え、一人でも多くの方々におぢばへお帰り頂いて、教祖にたすけて頂きましょう。
本年の具体的な活動目標である、「諭達」の六つの実動十万件を網走大教会に繋がるものが一手一つとなって必ず達成し、先程お話した大教会の心定め完遂へ向け、年祭活動仕上げの年にあたる三年目を精一杯通らせて頂き、ここ数年でこんなに一生懸命させてもらったことはないという一年にさせて頂きましょう。そして来年一月二十六日に迎える教祖百四十年祭の当日には教祖に安心して頂けるよう、教祖に大いに喜んで頂けるよう力一杯通らせて頂きましょう。
本年も道の上にまた大教会の上にお力添えを賜りますよう、何卒宜しくお願い致します。