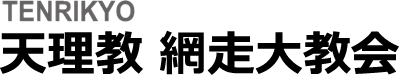大教会長様講話(立教187年11月号)
♦おつとめ
教祖のひながたの五十年を大きく前半と後半に分けると、前半にあたる天理教が始まった百八十七年前は、数々の飢饉で餓死する人が多い時代で「物を施して執着をされば、心に明るさが生まれ、心に明るさが生まれると、自ら陽気ぐらしへの道が開ける」と親神様が教えて下さり、教祖はとにかく困っている方々を我が子同様に思われ、施しに徹しました。その施し方は常識を超えており、明日食べる米まで施し、飲まず食わずの生活を二十数年通られたのです。
このひながたの前半では、人間は一番欲が深いため、困っている方へ施すことが、欲の心を捨てる心になり、欲がなくなれば陽気ぐらしの始まりになると教祖は教えて下さいました。
そして中盤から後半はまさに、只今我々が勤めたおつとめを、これも二十年以上かけて教えて下さいました。教祖が初めておつとめを教えて下されたのは、今から百五十八年前にあたる慶応二年(教祖六十九歳)になります。その後十五年以上の歳月をかけ、みかぐらうたや鳴物、おてふりを教えて下さり、おつとめを初めて教えて下さってから、九十歳でお姿を隠される明治二十年までの二十一年間に渡り、一貫しておつとめを勤めてくれと我々に望まれました。
ここにいる皆さんが今歌ったみかぐらうたは、教祖が教えて下さった歌になります。みかぐらうたは、漢字で神が楽しむ歌と書くように、我々が一生懸命に歌えば、神様が楽しんで下さる歌になります。
このおつとめについて、三代真柱様は「人間世界の平穏無事を願う、平和を願う、どこの国とも、どこの人とも、互いにたすけ合って暮すことを願うには、私はこのおつとめに頼るほかには道がない」とお話をされました。
そして「私たちの任務は、つとめを完成させることが最大の任務である。これは、本部といわず、各教会といわず、教会長、信者の別なく、一人ひとりが同じだけの重さを持った任務である。」ともお話し下さいました。
おふでさきに、
にちくにはやくつとめをせきこめよ いかなるなんもみなのがれるで (十-19)
※意味 おつとめを一日も早く実行するならどんな災難も皆逃れることができる
とのよふなむつかしくなるやまいでも つとめ一ぢよてみなたすかるで (十-20)
※意味 どんな難病や危篤な状態にある重い病気でもおつとめで、不思議なたすかりを頂くことができる
このつとめなにの事やとをもている せかいをさめてたすけばかりを (四-93)
※意味 このおつとめは、世界を治め理想の平和を実現させることができる。
又、教祖は「一つ手の振り方間違ても、宜敷ない。このつとめで命の切換するのや。大切なつとめやで。」と教えて下さるように、このおつとめを一つも間違えないように、真剣につとめれば命の切換えができ、どんな難も逃れ、医者が匙を投げたような病気でも奇跡が起きたすかる、そして世界中が治まってくると、親神様は仰っておられます。
このおつとめには我々では想像もつかないような、とてつもない力があるのです。
大教会を始め、各教会では朝夕と毎日必ずおつとめを勤めています。おつとめを勤める時は、必ず四つ手を叩いてから始まります。
四つ叩く柏手の一つ目は、神様と心を合わせる、二つ目は親に合わせる。三つ目は夫や妻に合わせる、四つ目は子供や、家族に合わせる。この四つを合わせて四合わせ(幸せ)となり、このことを日々、親神様、教祖にお誓いする為にまずは四つ手を叩くということを聞いたことがあります。
そして朝づとめでは、四拍手の後、親神様にはまずおはようございますと挨拶をし、「本日も網走大教会に繫がる人をはじめ、家族に繫がるもの、隣近所やそれぞれに繫がるもの一同が新しい一日を迎えさせて頂いたことにお礼申し上げ、その日の日付をお伝えし、只今よりお教え頂いたよろづたすけのおつとめを勤めさせて頂きます」とお願い申し上げおつとめを始めます。
又、おつとめが終われば、ない世界、ない人間をお創り下さいました元の神様、今も十全のご守護を下さいます実の神様、日々結構にお連れ通り下さりありがとうございます。本日も親神様へのご恩返しを心に、お望み下さいます陽気ぐらし世界実現の為、人たすけの御用にお使い下さいと今日の心定めをしてご祈念し四拍手をします。
次に教祖殿前に行き四拍手の後、教祖へおはようございますと挨拶の後「ご存命の教祖には夜昼の区別なく私どもを結構におたすけ頂き、新しい一日を迎えさせて頂き誠にありがとうございますとお礼申し上げ、今日の日付をお伝えし、本日もひながたを心の定規として通らせて頂きますので、教祖の手足となって人たすけの御用にお使い下さいますようお願い申し上げます」とご祈念させて頂き四拍手をします。
祖霊様の場合も同様に四柏手をして「初代真柱様をはじめ歴代の真柱様、本席様や中山家の霊様、歴代会長、役員、信者その他諸々の霊様のお徳のお陰で今日を迎えさせて頂いたことをお礼申し上げ、霊様が誠真実の心で伏せ込まれたこの教会で本日も神様の御用を勇んでつとめさせて頂きます」とご祈念させて頂きます。
夕づとめは朝づとめのご祈念に対してお礼を申し上げます。そしておつとめをしている最中、うっかりすると他のことを考え、心が親神様から離れることがあります。こうなると真剣におつとめを勤めたということにはなりません。
常に親神様に心を近づけて真剣におつとめをするにはどうすればよいのか。例えば第一節のあしきをはらうてたすけたまへ てんりわうのみことを一回ごとに心の中で、くにとこたちのみことさま 人間身の内の眼うるおい、世界では水の守護の理のご守護をありがとうございますと、そして二回目三回目と続き二十一回まで、順番に十全の守護の説き分けを唱えていれば、おつとめの最中に親神様・教祖から心が離れることはありません。
第二節のちょとはなし、第三節のたすけせきこむも、常にかんろだいを目の前に想像しおつとめを勤めさせて頂きます。真剣に勤めれば様々なたすかりを頂けます。
当たり前のご守護を頂こうと思うなら、当たり前にしなければならない朝夕のおつとめをする必要があります。当たり前のご守護が頂けないのは、当たり前に勤めなければならない、朝夕のおつとめをしていないからではないでしょうか。
これは私の勝手な悟りですが、私は朝夕のおつとめのご祈念の際、人のたすかりをお願いすることはありません。先ほどお話しした通り、親神様・教祖へはお礼とその日の心定めのみであります。
人のたすかりを願うには、朝夕のおつとめとは別に改めてお願いづとめをさせて頂くことが大切ではないでしょうか。我々ようぼくは一日最低一回は、人の為に祈るお願いづとめをする必要があります。自分一人で勤めれば、お願いづとめは五分で終わります。
ようぼくは一日千四百四十分あるうちの、たった五分位は、人の為に祈りを捧げる時間にする必要があるのではないでしょうか。
我々の曽祖父や曾祖母の時代、おさづけは入信して随分たってから戴いています。網走大教会初代会長脇本熊吉先生は、天理教に入信してから十四年後の明治四十年十一月二十六日、二代会長三幣勝五郎先生は入信後九年たった明治四十年三月五日におさづけを頂きました。
ではこの両先生は、おさづけを頂くまでおたすけはしていなかったかというとそうではありません。おさづけを頂く前から、医者に匙を投げられた病人や苦しみ悩むなかどん底の生活をしている方へ、お願いづとめのみでバンバンご守護を頂いていたのです。
二代勝五郎先生はとにかく、重病人や大切なお願いをする時は、羽織袴に着替え、神様にお供えする神饌物もおつとめの度に全て取り替え、まさに命がけでおつとめをしていたそうです。
我々も先人を見習い、せめてお願いづとめをする際は、病気や悩み苦しむ人の氏名や年齢、病気や悩みの内容を紙に書き、神様に供えておつとめをすべきではないでしょうか。
更に病気の方や悩んでいる方が、信仰を持っている人であればその方に、自筆で神様との約束になる心定めの紙を書いて頂き、紙の裏には本人に反省の心として、思いつく度にさんげを一つずつ書いて頂き、親神様・教祖へ心定めとして約束をし、その約束を実行してご守護を頂けない時は、更に心定めを一つ増やし神様との約束をやり直して実行に移せば、必ずご守護を頂けるのです。
命に関わるような病気や、人の力ではどうにもならない悩みなどの場合は、何日間つとめると日にちを仕切って、一日にお願いづとめを六回勤めれば、必ずご守護を頂くか、ご守護を頂く方へ導いて下さいます。
人へのお願いもそうですが、自分自身生きていますと、苦しいことや辛い時が多々出てきます。そういう苦しい時、辛い時は、天理市にあるおぢばへ帰り親神様がおられるかんろだいの前でおつとめをし、人様のたすかりを祈る。
そうすれば自身の心のほこりを払うことになり、心の掃除をすることになります。そして胸の掃除をして心が澄み切ったなら、我々人間すべての母親である教祖へ会いに教祖殿へ行き、たすけて下さい、私の苦しみ悩みを背負って下さいとお願いすれば、教祖は子供が可愛くてしかたないという親ですから、我々の苦しみ悩みを全て背負って下さり必ずたすかるきっかけを色々とつくって下さったり、たすかりの為に人と出会わせてくれます。
おぢばへ行けなければ、近くの教会へ何度も通い同じようにおつとめをして、教会におられる教祖の前で、たすけて下さいとお願いすれば必ず教祖が苦しみ、悩みを背負って下さいます。
我々はもっとおつとめと向き合う必要があります。初代真柱様の奥様である御母堂様はおつとめについて「昔習った頃は、何時土足の人が上がり込んでくるか分らんので、皆タスキ掛で稽古したんや。今日こうして、昼日中、誰にも文句言われず、教祖の辛苦しておつけ下さった手を移してもらえるのやから、結構やで、しっかり稽古せないかんぜ。」とお話し下されました。
教祖がお姿があった明治の頃は、神道が国の宗教でしたのでそれ以外の宗教は弾圧する時代でした。特に天理教や他に数ヵ所の他宗教は、政府からかなり厳しい弾圧を受けていました。
その頃、今勤めたおつとめは弾圧の対象になり、おつとめを勤めただけで警察に捕まり留置所へ入れられる状態でしたので、御母堂様は昔と違い今は、昼間からおつとめをしても警察に捕まることもないし、誰に文句も言われることもないなから、教祖が苦心して直接教えて頂いたこのおつとめをさせてもらえるのだから、しっかり稽古をしないといけないと仰せられたのです。
先ほどもお話ししましたが、「一つ手の振り方間違ても、宜敷ない。このつとめで命の切換するのや。大切なつとめやで。」とのことでありますので、命の切換え、運命の切換えをさせて頂くためにしっかり、おつとめの稽古をさせて頂きましょう。
最後になりますが、諭達第四号の締めくくりに真柱様は「ご存命でお働き下さる教祖にご安心頂き、お喜び頂きたい。」と仰られました。教祖にご安心頂くということに関して、三代真柱様は「私たちは、教祖がお望みになるつとめの完成に向かって、努力を重ね続けてこそ教祖に安心して頂けることと思案する」とお話し下されました。
教祖にご安心頂くには、やはりおつとめがしっかりできるようになるために努力をすることです。そして教祖にお喜び頂くにはどうすればよいのか。それはおさづけを取り次ぐことです。
そして我々が頂いているおさづけは、てをどりのさづけになります。このおさづけはまさにおつとめの理をそのまま、病人の患部に取り次ぐことになります。おつとめをしなければ、おさづけの効能の理は頂けないのです。
本日勤めた月次祭は、一番大切なおつとめになり、朝夕のおつとめ、お願いづとめとを含め、より一層真剣におつとめを勤め、再来年一月二十六日の教祖百四十年祭当日には、教祖にご安心頂き、お喜び頂けるよう、その日を楽しみに残りの年祭活動期間を勇んでつとめさせて頂きましょう。