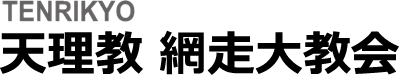大教会長様講話(立教187年2月号)
一月は、諭達第四号で「明治二十年陰暦正月二十六日、子供の成人を急き込まれ、定命を縮めて現身をかくされたが、今も存命のまま元のやしきに留まり、世界たすけの先頭に立ってお働き下され、私たちをお導きくだされている。」と真柱様がお示しの通り、本年は教祖がお姿を隠されてから百三十八年目になります。
我々お道を信仰するものは、二年後の教祖百四十年祭を目指して昨年からより一層力を入れて通らせて頂き、現在年祭活動は二年目に入りました。
一昨年、三年千日が始まる前年の十月に真柱様は、我々がこの三年間どういう心構えで通らせて頂いたらよいかという指針を諭達第四号においてお示し下さいました。諭達第四号ではひながたという言葉が、八回出てきます。特に我々ようぼくは諭達でお示し下さっていることを、三年間心に置いて通らせて頂かなければならないので、やはり教祖ひながたを身近に感じ、実行させて頂くことが非常に重要になります。
ひながたといえば教祖伝逸話篇がわかりやすく身近に感じると思います。逸話篇は教祖九十年祭の時に発刊されたもので二百話のお話が納められておりますが、一番のお話よりおおよそ年代通りの順番になっています。
まずは、逸話篇の冒頭のお話に触れさせて頂きますが、逸話篇七番に「真心の御供」という逸話があります。これは教祖は見抜き見通しであったということと、神様へ御供をする時の心構えについて教えて下さっております。
この「真心の御供」のお話は、初めて信者が教祖へお米四合を持って御礼参りされた後の話しで、教祖が六十一才から六十三才位の時のお話になります。
教祖を含め家族の皆さんは、貧のどん底を通られている頃でまだ明日の食べるお米もないというような時代の話しと推察できますが、ある年の暮れに一人の信者が立派な重箱に綺麗な餅を入れて「これを教祖にお上げしてください。」といって持ってきました。娘のこかんさんは、早速それを教祖にお見せしましたが、教祖は「ああそうかえ。」とだけしか言いませんでした。
それから二~三日して、又、一人の信者がやってきました。そして粗末な風呂敷包みをだして「これを、教祖にお上げして頂きとうございます。」と言って渡しました。中には竹の皮にほんの少しのあん餅が入っていました。そして、こかんさんが教祖にお見せすると、「直ぐに、親神様にお供えしておくれ。」と非常にご満足の様子だったそうです。
後で分かったのですが、最初に餅を持ってきた人は、相当な家の人で正月の餅をついて余ったので、とにかく教祖の所へお上げしようとなったのですが、後の人は貧しい家であったけれども、やっとのことで正月の餅をつくことができたので、「これも、親神様のお陰だ。何はおいてもお初を。」というので教祖に持って来ました。
このお話を読んで分かるように、教祖は何事も見抜き見通しで人々の心遣いと行いは、すべてご存知でありました。これは現在も同じで、教祖は姿形が見えないだけで、魂は生き通しで我々の考えることや、することは全て教祖に筒抜けなのです。
昔の人はよく御天と様が見ているよと話をしていましたが、まさに教祖が見ておられるのです。教祖はもちろんのこと親神様も我々の考えることやすることなど、心をどういう風に使っているかは、筒抜けで全て分かっておられます。
逆に考えると、仮に我々人間の心遣いが分からないまま身上や事情を見せられるとなればたまったものではありません。もし親神様が我々の心使いを知らずに、気まぐれで人間に身上や事情を見せるとなるとどうなるでしょう。私たちは日々どう暮らせばよいのか全くわからなくなります。
人間の世界は世の中で悪いことをしている人すべてを、法の裁きにかけることはできません。我々の知らない所で罪を犯している人も大勢いますが、反対にどれだけ善いことをしても世の中全ての人に拍手をされ称賛されるとは限りません。
しかし、先程お話をしました御天と様が見ているではありませんが、親神様が善悪共にすべて見抜き見通しで筒抜けだからこそ、世の中の人も神様は善は善、悪は悪で平等に見てくれているとなり、安心して人生を送れることになります。
常に親神様・教祖は我々の心遣いをご覧になっているという実感をもつことが大切になります。しかし常に親神様、教祖がご覧になっているというと、我々人間はどうしても悪い方に考えてしまいます。
何か悪い心遣いを見られているのではないか、この通り方は間違っていて、病気をもらってしまうのでは、災難にあってしまうのではと考えがちになりやすいものです。
しかし、逸話篇には人間の悪行をこらしめるということより、善い行いをご覧になっているというお話の方が多いのです。
例えば、逸話篇百六の「蔭膳」という話では、教祖が十二日間、奈良監獄所へ御苦労下されたとき、梅谷四郎兵衛さんは、差し入れをするため毎日朝暗いうちから起きて、監獄所までの十二キロの道を歩いて行かれました。ある時は、監獄所で挨拶をしなかったと言って脅かされ、泥の中へ手をついて謝り、ようやく帰らせてもらったことさえありました。
それから教祖はお元気で自宅にお戻りになり、四郎兵衛さんを呼び「四郎兵衛さん、御苦労やったなぁ。お陰で、ちっともひもじゅうなかったで。」と仰せられました。四郎兵衛さんはその時、差し入れを届けていただけで、教祖には一度もお会いしていないのに、なぜ自分が差し入れをしていると分かったのだろうと思われたのでないでしょうか。
そして更に後でわかったのですが、教祖が監獄で御苦労下さっている間、梅谷四郎兵衛さんの奥さんが、大阪で毎日教祖が目の前におられる想いで蔭膳をされていました。
この時、四郎兵衛さんと奥さんが語り合う中で改めて、教祖はやはり見抜き見通しなんだと気づかせて頂いたと思うのです。このお話ひとつとっても、教祖は常にすべての行いをご覧になっているということがわかります。
ここまでの逸話は神様が我々をどう見て下さっているのかという話でありますが、では次に神様は我々人間にどういう心をかけて下さっているのかというお話です。
逸話篇百六十番のお話に「柿選び」というお話があります。この逸話篇は、柿の旬の時期にお盆に載せてあった柿を、教祖が桝井さんに上げようとして、そのお盆の上の柿をあちこちと眺めて選んでおりました。桝井さんは教祖でもやはり選ぶんだなあと思っていると、教祖は一番悪い柿をとって、残りの柿を見て一つお上がりと柿を下さったのです。
桝井さんは、教祖も柿を選ばれるが、教祖がお選びになるのは、我々とは違って一番悪い柿を選ばれる。これが教祖の親心なんだ。子供にはおいしそうなのを後に残して、これを食べさせてやりたいという、これが本当の親心だと思われました。桝井さんはこの教祖の様子を深く肝に銘じて生涯忘れなかったそうです。
このお話も非常に分かりやすく身近なお話になりますが、現代に生きる我々がこのひながたを実行に移そうとするとき、例えばスーパーに買い物に行ったとします。牛乳を買う時、卵を買う時皆さんはまず何を見るでしょうか。牛乳や卵の種類を見る方もおられますが、賞味期限を見る方が多いと思います。
皆さんはどうでしょう。賞味期限が迫っているもの、賞味期限がまだ十分にあるものどちらを手に取るでしょうか。大概の方は賞味期限がまだ十分にあるものをとると思いますが、もし教祖がスーパーに買い物に行かれたらどうされるでしょうか。きっと賞味期限が迫っているものを選び、後で買う人に賞味期限がまだ十分にあるものを選んでもらえるようにされるのではないでしょうか。
もう一つ例を挙げますと、皆さんはドラッグストアやホームセンターへ車で買い物に行ったとき、どこに車を止めるでしょうか。なるべくお店の玄関に近い所、近い所に車を止めるのではないでしょうか。
教祖が車で買いものに行かれたら、きっとお店の玄関より少し遠い所を選ばれ自分は少し歩かれ、後から来る人に少しでも玄関の近くに車を止めてもらえるようにするのではないでしょうか。
教祖がもし、電車に乗っていたら、もし車を運転していたらと考えると、教祖のひながたを実践することはそんなに難しいことではありません。
我々はついつい、教祖のひながたは人間では到底通られないと思いがちです。貧に落ち切る為、家にある金品や家財などありとあらゆるものをすべて困っている人々へ施してしまったり、七十五日間の断食や腕力ある二十代の青年と力比べをして若い人たちを負かしてしまったり、監獄所に何度も御苦労されたりと教祖のひながたは到底真似ができないと思っておられる方もおられるでしょう。
しかし、先程、真心の御供や蔭膳、柿選びなどを例に挙げましたが、よくよく考えれば、日々生活をする中で教祖のひながたを実践しようと思えばいくらでも出てくるのです。
真柱様は諭達で「ひながたを通らねばひながた要らん。(略)ひながたの道より道が無いで」と仰られています。教祖年祭の三年千日は、ひながたを目標に教えを実践し、たすけ一条の道を活発に推し進めるときである。ともお示し下さっているように、ひながたをどのように身近な生活に生かすことができるかをひたすら考えて、ひながたを実践し、一心一家の都合は捨て、我が事は後回しに三年千日二年目の本年も、全教会心定めの達成を目指し、網走大教会が一丸となって、年祭活動に伏せ込ませて頂きましょう。
本年一年も何卒宜しくお願い致します。