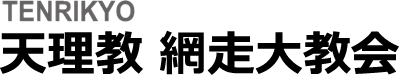大教会長様講話(立教186年2月号)
♦教祖年祭の歴史♦
教祖の年祭は、今から137年前、明治20年陰暦正月26日教祖がお姿をお隠しになられて後、本席飯降伊蔵先生を通して「子供可愛い故、をやの命を二十五年先の命を縮めて、今からたすけするのやで」とのお言葉から、世界中の人間をたすけたいという、たすけ一条の親心をご本部の先生方が聞かせて頂き、その後我々の初代や二代、又諸先輩先生方へと伝わり、教祖の年祭を命懸けで歩まれてきたわけであります。
教祖1年祭は、明治21年陰暦正月26日に執行され、教祖を慕って集まる人は、約3万人もいたそうです。しかし当日は斎主を巡る問題から櫟本警察署長以下、配下の巡査8名が祭場に現れ、年祭中に祭員の取調べを始め、1年祭は中止になりました。
教祖5年祭は、明治24年3月6日(陰暦正月26日)から8日までの3日間執行されました。この年祭では10数万人の人が帰えられたという記録が残っております。先の1年祭では、警察が途中で割って入り中止になりましたが、5年祭までに神道本局直轄天理教会として地方庁の認可も得て、1年祭とは打って変わり警察の巡査2名が徹夜で警備に就くという有様でした。この年祭の2年後、明治26年に目の患いから、網走大教会初代脇本熊吉先生が入信されました。
教祖10年祭は、明治29年3月9日(陰暦正月25日)に執行され、参拝者数は20万余人にもなったと記録されています。そして北は北海道、南は沖縄又海外までと教勢が広まりました。教祖がお姿をお隠しになられた頃の信者数から比べると、信者は300万人以上になり、1年祭の時に約4万から5万人だった信者が、たった10年で60倍以上になったのであります。当時の日本の人口が4千万人位でしたので、人口の7%位がお道の信者であったということが分かります。この頃の明治31年に網走二代三幣勝五郎先生が14歳で入信されました。又、明治34年に脇本熊吉先生は、網走にて布教を開始されています。
教祖20年祭は、明治39年2月18日(陰暦正月25日)に執行され15万人の参拝者と記録があります。この時の年祭は、10年祭直後の内務省秘密訓令によって政府から弾圧され、又、世上からは新聞等で悪口を書き立てられる時代でありました。この年祭で、当時22歳であった網走二代三幣勝五郎先生は、徒歩でおちばがえりされ初席を運ばれました。
又、明治44年には、脇本熊吉先生を初代とし、網走宣教所が開設されました。
教祖30年祭は、大正5年1月25日に執行され、参拝者数は20年祭と同じ約15万人でした。網走では、年祭の翌年大正6年、宣教所にお目標様がお鎮まり下さり、名実共に、ぢばの出張り場所となりました。
翌年には、二代真柱御一行様が初めて網走へお入り込み下さっております。
教祖40年祭は、大正15年1月15日、20日、25日の3回にわけて執行されました。この年祭より5年前から1つの目標を立て、全教が一丸となって年祭に取り組むという体制になり、40年祭当時は活動目標の大きなものとして、「教勢倍加運動」と「海外布教」の提唱でありました。年祭の参拝者数は延べで65万人を突破し教勢倍加の実績を残す結果となりました。20年祭・30年祭と停滞していた教勢も、この頃から再び息を吹き返してきたようです。40年祭では、二代三幣勝五郎先生を筆頭に網走として初めての100人を超える団体でおぢばがえりをさせて頂きました。
教祖50年祭は、昭和11年1月26日から2月18日(陰暦正月26日)までを祭典期間として執行され、今までお教え通りにつとめられなかったおつとめが、かんろだいを芯につとめられ、ほぼ復元されました。この50年祭では、網走から三幣勝五郎先生を始め部内会長15人が昇殿参拝をさせて頂きました。
教祖60年祭は、昭和21年1月26日から2月18日まで執行され、この年祭は、日中戦争や太平洋戦争の渦中にあって、50年祭の勢いとは異なり非常に寂しい年祭であったそうです。しかし昭和20年には戦争が終わり、教会本部は直ちに教義の復元に力を注ぎ、婦人会や青年会も復元し、いわば復元の年祭だったのであります。
教祖70年祭は、昭和31年1月26日から2月18日まで執行され、参拝者数は60年祭と比べると、100万人以上の帰参者であふれかえりました。「屋敷の中は、八町四方と成るのやで」という教祖のお言葉の実現を志し、おやさとやかたの建設に着手することが決められ、約150万人のひのきしんのもと、1年半弱でおやさとやかたの第一期工事、真東棟をはじめ、東左第1から5棟までが普請されました。これは今の別席場付近のやかたになります。また、稿本天理教教祖伝の刊行や、2時のサイレンもこの年祭の年から鳴らすようになりました。
網走大教会は教会として初の大規模団参となり、関東の帰参者も一旦網走に集まり、全員揃って出発し、心定めを上回る704名というご守護を頂きました。
教祖80年祭は、昭和41年1月26日から2月18日まで執行され、復元の徹底による心の成人をさらに掘り下げて、信仰の充実が図られ、海外布教も一段と活発になり、海外伝道部にアジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニアの5課が設置され、又メキシコ、パラグアイ、アフリカ、ペルーなどへ教線を伸ばしていきました。当時網走からは、1月20日に3代三幣かく先生を筆頭に第一陣866人、第二陣は、2月12日に803人がおぢばへ帰らせて頂くという、前人未到の数の方が帰参され、現在とは比較すら出来ない程の大きな団体になりました。又この年祭の年に、進め網走の歌や網走月報が刊行されました。
教祖90年祭は、昭和51年1月26日から2月18日まで執行され、三年千日と仕切った年祭活動のスタイルに変わりました。稿本天理教教祖伝逸話篇が刊行されたのもこの年祭の時であります。帰参者の数は、200万人を超える参拝者でおぢばがあふれかえったそうであります。別席者の数は、海外も合わせなんと17万人以上という記録があります。
これから更に教祖100年祭・110・120・130年祭を経て、現在140年祭三年千日の活動が始まろうとしておりますが、年祭のたび、さまざまな節があり大きく飛躍してきたお道も、現在では教勢に勢いがない状態になっています。親神様からのご守護は、昔も今も変わらないはずなのに、なぜ今はご守護を頂けないのかと考えれば考えるほど、なぜだろうと難しく思っていましたが、教祖はこの道を、ごく簡単なことから身をもってお教え下さりました。簡単にわかりやすくと考えた時、教祖のひながたもそうですが、身近な話を振り返るのもよいのではと思い、網走大教会の初代会長をはじめ二代・三代会長の通られた道のりを少し振り返ろうと思います。
まずは初代会長の苦労です。初代脇本熊吉先生はひたすら、教祖のひながたのみを心に置き、おたすけに命懸けでありました。扉もない小屋で寝食をし、冬はマイナス20度、30度の中、もう一人の布教師である小山福太郎先生と抱き合いながら暖を取り、毎朝生き死にを確認しておたすけに出ておられました。初代の伏せ込みがあるから今の大教会があるのです。そして理の立て方において、二代三幣勝五郎先生は、本部や上級から巡教の先生をお迎えする時、巡教を頂く体制に入り、無事到着するよう、お願いづとめをするのが常であったそうです。
又、三代三幣かく先生は、朝夕のおつとめに関して、「時間ぎりぎりにきて、付き合い程度のおつとめは、おつとめとは言えません。少なくとも10分前には来て心を鎮め、おつとめの時間まで待たせて頂きなさい。」と住み込みの方へ仕込んでいたそうです。また、信者さんに対する接し方に関して、二代三幣勝五郎先生は、「お供えを出す身になったら大変なんですよ、容易ではないんですよ。」と神様のお供えは置き場所にも注意し、非常に丁寧に取り扱い、5銭、10銭という小さな金額でも頭を垂れ、お包みを丁重に押し頂き、数分間も相手のご苦労と真心に感謝して、「ご苦労様でした。またつとめさせて頂きましょうね。」というのが常で、この態度を見た信者さんは、今度はもっとつとめさせて頂こうと思ったそうです。
今はご守護が少ないとよく口にしますが、私は親神様・教祖に対して、又、信者さんに対してここまで心を遣っているのかと考えた時、非常に反省の気持ちでいっぱいになります。我々の信仰には教祖のひながたがあり、そのひながたを命懸けで辿った先人先生方がいて、その伏せ込みのお陰で、今の網走大教会が成り立っています。そしてその先人先生達は教祖の年祭毎に、まさに命懸けで教祖へのご恩を返す精神をもって通って来られました。
いよいよ今月のご本部の春季大祭より三年千日の年祭活動が始まります。まずは1月26日におぢばへ帰り、教祖よりお許し頂いた、網走大教会に繋がる我々教会長がご本部の教祖殿へ足を運び、それぞれの教会で定めた心定めを持参し、教祖の御前で「本日よりまずは一年目の心定めを勇んでつとめさせて頂きます」とお誓い申し上げ、年祭活動のスタートを切らせて頂きましょう。